newworld
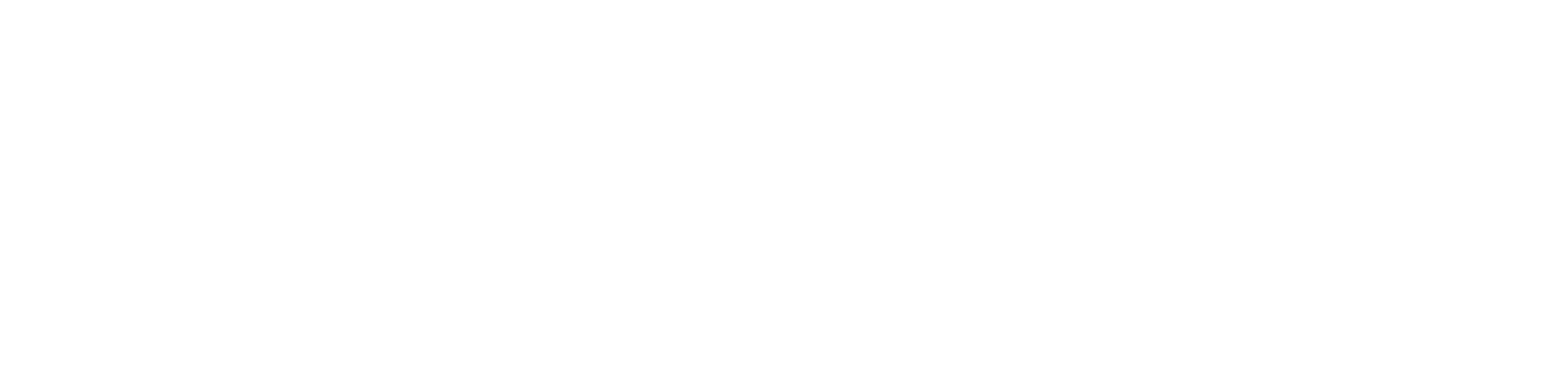
Happy NeWORLD

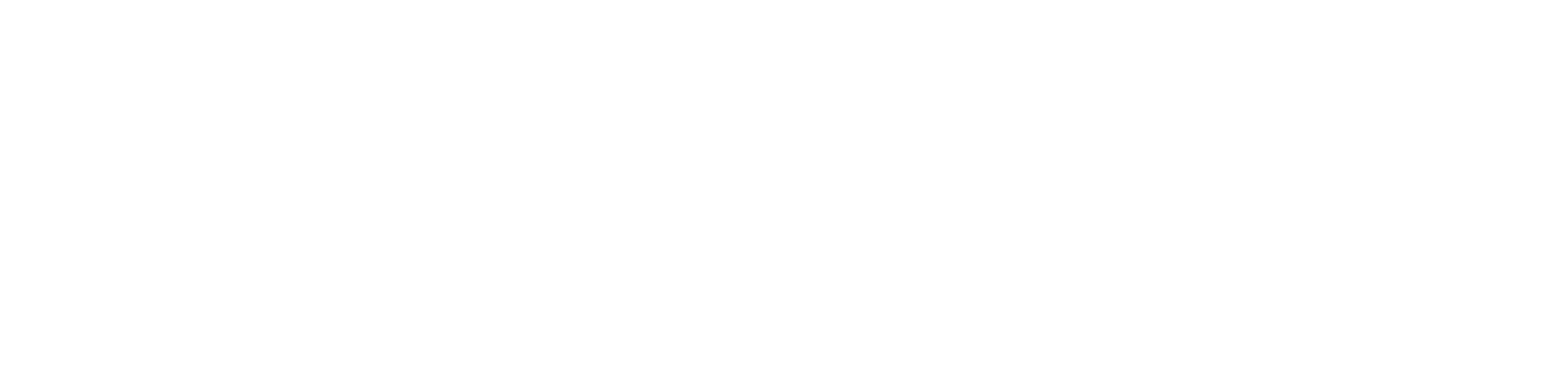
Happy NeWORLD

七時間の大手術を終え、僕はICUで目を覚ました。しばらくすると妻が娘二人を連れて面会にやって来た。三人ともマスクをしている。寝たままの姿勢で上体を起こせない僕からは妻と長女の顔は見えるのだが、長女よりまだ頭ひとつ分背が低い次女は頭のてっぺんしか見えない。それで妻が次女を抱っこして顔を見せてくれる。 *1
デモを見てお祭りみたいだと言う人がいる。お祭りみたいで楽しそうだと賛意を込めて言うひともいれば、騒ぎたいだけだろと揶揄として言うひともいる。僕も祭りは好きだ。子供の時は山車を引いてお菓子をもらうのがうれしかったという程度だったが大人になってからひょんなきっかけで大人神輿を担ぐことになった時、自分はこれほど祭りが好きだったのかと驚くほどの体験をした。ぶっ倒れる寸前まで体力を使い果たすことが自分自身を何かに捧げているかのような気持ちにさせた。後に何も残らない忘我の境地。それが祭りだとすればデモは祭りには似てないと思う。
では、デモに似ているものが祭りの他に何があるだろうか。自分が実際にデモに参加している時に「これはあの時に似ている」と思ったことが一度だけあった。 *2「証言」のファースト・テイクを聞いたのは七月の「チェック・ユア・マイク」の時のことだったと思う。自分のライブを終えてブースでDJをしていた僕のところへ、興奮した様子で現れたデヴ・ラージが「石田さん、これかけて」と一本のカセット・テープを差し出した。それが、その日、録ってきたばかりだという「証言」のテープだった。「証言」は東京FMで不定期にオン・エアされるようになっていた「ヒップホップ ナイトフライト」で紹介されたこともあり、「鬼だまり」などのイベントで欠かせない曲になっていった。 *3
僕は子供の頃にTVの歌番組で野坂昭如が「マリリン・モンロー・ノー・リターン」を歌うのを見たことがある。ラジオでも何度でも聴いたことがある。僕は自分の曲「迷子のセールスマン」で、「マリリン〜」のサビのフレーズ「この世はもうじきお終いだぁ」を借用させてもらっている。特に考えてのことではない。「マリリン〜」に深い思い入れがあったわけでもない。バック・トラックのサンプリングのループを繰り返し聴いているうちに、自然に「この世はもうじき〜」と口をついて出てきたまでのことだ。歌というのはそんな風にひとの体に残ってゆく。 *4
翌朝、僕は七時に起き、目を覚ました娘にミルクをやり、食事をして、まだ寝ている妻に「行ってきます」と小声で声をかけ部屋を出た。マンションの階段を降りながら肩にかけたカバンのポケットからCDウォークマンのイヤフォンを取り出し、からまったコードをほどく。コードをほどき終わりイヤフォンを耳に入れ、歩道橋の階段を上がりながらCDウォークマンのプレイボタンを押す。CDウォークマンには前々日仕事帰りに新宿のタワーレコードで買ってすぐにセットしたアメリカ南部のヒップホップのCDが入れっぱなしになっている。帰り途、途中まで聞いて、家に着き、ドアを開ける前に停止したところから再生が始まる。殺伐とした血も涙もない音楽が、部屋を出てひとりに戻った自分に不思議となじむ。 *5
2018年1月24日に地球から離れてしまった、ラッパー/小説家/アクティヴィスト、ECDのアーティストとしての相貌との改めての邂逅がこの連載の狙うところである。そのことは、自然と日本においてのヒップホップの成り立ちや変遷を振り返ることへも私たちを導いていくだろう。例えば、ECDは1970年代初めのアメリカで生まれたヒップホップに魅了され日本でその実現にいち早く取り組みながら、実はそこから繰り返し“降りた”人物でもある。
彼のアーティストとしての名前であるECDを知っており、その名前の下で発表されてきた彼のアートに少しでも好意的もしくは否定的な印象を持つ人々の多くは、彼が長期間にわたって文章を書いていたことを知っている。ここにそれらを写し記し繰り返すことさえ躊躇うような私的かつ赤裸々なことども――それらはみな本当のことなんだろうか?――から、生前の彼に影響を与えた多くのアート作品についてまで、彼は多くの言葉を使い単行本や雑誌やウェブの記事として書き遺していった。
私も、他の少なくない人々も、これまでも彼の遺した音楽作品のみならず、こうした無数の言葉を引用し並べ替えて編集し、彼の生前から今に至ってもなお、彼を自分たちのまぢかに再-現前させようとすることに利用してきた。世間というものがあるとして、現在その場で流布している彼についての“パブリック・イメージ”[*6]は、彼が遺した音楽と“文学”作品に因っているといえる。例えば、ECDは“日本語ラップの草分け”で“ヒップホップ・レジェンド”であり、彼が大量に遺していった音楽と言葉は “新しい姿のメッセージ”や“ラッパーのリアル”で“ストレートでうそ偽りない”――といった短いフレーズにまとまり流通していく幾つもの通念もその例外ではない――しかし、それは十分ではないと私は感じる。
彼がまだ生きていて、中目黒や下北沢の路地でふっと遭遇することが決して珍しくない日常だったあの昔から、実はそのことを薄々と感じていたとここに書くなら笑われてしまうだろうけど、笑われるにあたいするから記しておく。2015年に久しぶりに彼とベンチ席に向かいあって座って話す機会を得たときも、やはり自分の勝手な頭にあったことをふっと「人間ドックでなくてもいいのだから簡単な健康診断を受けるのは大切だと思います」と彼に話したとき、彼が無言のまま少しびっくりするような表情になった、その前後にあった時間にも、それは十分ではないと私は感じていた。
遅きに失していることは恥ずかしい。それでも、この連載では、私たちにも残されている彼の音楽/文学作品から溢れる言葉を多く引用していく。しかし、それは私が隠された石田義則の素顔をメディアに引き摺り出す特権的な力を持つポジションにあって、他の人の知り得ぬインサイダー情報を持ち出してシェアすることにより私と読者のみなさんの“エンタメ”とお得になるからではない。そうではなく、まだ始まったばかりの21世紀に生きる私たちを相応しいアクションに導いてくれることがあるとしたら、アートを解体し再構築する試みに違いあるまいという信仰による。即ち、このテキスト全体が、チャックDの言葉を借りるのなら、サウンドにおける“サンプリング・スポーツ”[ *7]の大きな影響下にあるに過ぎない。ECDもまたそうした文化の保存と更新のありようを自らの出発する契機としたことはいうまでもない。それは、私たちそれぞれが選べない環境からともかく始めるしかなく、文化的な構築体として生きていくという考えと関係する。
Public Enemy “Caught, Can We Get a Witness?”, 1988
十分でないと先ほど記したのは、その時ECDの膨大に残された言葉や音を私たちが論じ尽くしたという状態からほど遠いのではないか、ということだ。そして、アートにしても生にしても、論じ尽くすということはあり得るかとのことに思い至るなら、残された私たちそれぞれがなすすべは、解体と再構築の形をとる質問をし続けることで、自分らの目先の手形のために似て非なるそれぞれの紋切型を恣意的に捏造し切り売りすることでは少なくともない。そしてECDの生涯を賭けた運動と作品を巡る言葉が一旦始まったならば、それは一定以上の長さを持つべきであり、力及ばずとも、むしろだからこそ、何度でも繰り返されるラディカリズムへ向かう必要があるのではないか。
時を遡る。ECDとの個人的な思い出を超えるように時を潜り、昔々、ECDの思春期である、日本の経済の高度成長期である1970年代の始まりへ遡る。そして、大阪女子大学国文科を卒業、その初期においてまず詩人、翻訳、そして1960年代に美術評論家として活動を始めた日向あき子が1971年暮れに出版した一冊の本へと向かう。その『原始の心』は、美術においてのプリミティヴィズムにまつわるテキスト群のパートから始まり、その中程ではロックとジャズを扱い、後半はファッションやデザインについて割かれている。
では1950年代の後半、もしもそのころ私が何かについて書いていたとすれば、それは何についてであったか。あのビートたち、ジャクソン・ポロックや、ジャズ、アレン・ギンズバーグや、ジャック・ケラワックについてだろうか。もちろんそれはわからない。だが、ロックについて語るとすれば、当然そこまでさかのぼることになるだろう。あのころ何ごとかが始まった。過去のコンテキスト、過去の価値観からふっきれた何かが始まったのである
いまロック・シーンに立ってみると、あのころから、無署名の巨大な意志とでもいったものが歩き始めたのがわかる*8
それを彼女は「文化のメイン・ストリートとして二千年近い伝統をほこっているあの文化」とは「ちがう文化」かつ「合理性と機械化のヨーロッパ的文脈とは縁をきろうとしているもう一つの文化」だと考え、「やがてこれが『サブ』ではなく主流になるのだ」という。「ビートニク、ポップそしてロックはまた、プレスリーや、文化人類学の復活や、原始に帰れや、マーシャル・マクルーハンや、フランツ・ファノンや、反戦やヒッピーと、網の目のように結ばれている。それはまたドラッグ・カルチュアや環境芸術化、複製文化、イデオロギーの終えん、禅や老荘思想、黒人文化、コミュニケーションの迅速、情報社会とよばれるものや大学問題や新しい性の考え方や、ニューファッション、アンダーグラウンド・シネマ、テレビ、漫画、都市化、ビートルズ、感覚型全人生、テクノロジー、等々の貴重な財産目録をもち、これら微妙な網の目で結ばれている」*9
日向あき子が思いつくままのよう無造作に項目を並べ記すのは、目まぐるしくも交錯し主体たる感覚すべてに向かい訴えかけてくる新しい世界のありようを伝えたいがためで、そのうえ「このうちどの一つを引っぱっても、鋭敏にすべての部分が振動し、からまってくるからである」。
このような世界の看取りは日本国内で日向だけのものではなかっただろうが、日向の要約は優れて過不足がない。それがここで抜粋される理由のひとつである。それは、主に写真と実験映像を通じてサンフランシスコやニューヨークを日本に持ち込みそこに『幻覚の共和国』を視た金坂健二から、ロカビリー/ファンキージャズの鳴り響く時代からキャリアを始めカナダのナショナルチャートで成果を出した内田裕也と彼のフラワー・トラヴェリン・バンドへ、そして活動を始めたばかりながら騒動を巻き起こしていたロック・バンドのキャロルに自らのパリのショウのステージを割り当てた山本寛斎までが捕らえ視えていたものへ繋がる。また、文学という日向による“文化のメイン・ストリート”にあったジャンルを振り返っても、例えば、医師から批評/小説家になった加藤周一がメディアとスチューデントパワーについて書き遺した“紅色娘子軍、ゴダールおよび仏像” [*10]の観察にも通じていく。
『原始の心』――音楽学や社会学のチャールズ・カイルやトリーシャ・ローズなどの仕事を経て今では多くに受け入れられている音楽へのリズムの構造を基礎とするアプローチへの目配せや、同時にそれを想像上の固着した“黒人性”に置き去りにしたままにしない気配りなど、今ではほぼ絶版となった彼女の著作や散逸したその初期の詩作品への興味を湧き立てるにこれは十分な俯瞰を見せる。しかし、ここで彼女が扱う、例えば、ルイ・アームストロングでもピンク・フロイドの音楽でも、その内容ないしは形式を裁断しようとせずに彼女の筆致は周囲を迂回しがちである。『原始の心』を読む限り、意図的に、日向は“鋭敏にすべての部分が振動し、からまってくる”魅力を囁きながらも“微妙な網の目”を解きほぐそうとしない。“サブ”に触れて愛撫が許される手前で距離を測る。
その晩年“にっぽんポッピズム”なる概念――おそらく再びサブ・カルチャーとの距離が正確に測られた――を中心とした著述を構想していたという日向の解釈にある欠落の構造は、革命があらかじめなかったように予定され、ゆえにそこにその失墜はなく、すべきブルジョワジーのノスタルジーのよう追憶の甘美さはあれども脈動に欠き歴史性へと赴かないことに因るのではないか。『原始の心』出版時には上映が留保されていた足立正生と松田政男らの不可能性を映しえたと愕然とする『略称・連続射殺魔』、翌年の足立正生脚本に若松孝二監督による『天使の恍惚』の政治と性と暴力/倒錯の行く末など、同時期の大島渚、吉田喜重、それに金井勝などが残した映像と並べるまでもなく、この問いを提出させるに十分ではないだろうか。
『天使の恍惚』のモノクロームとパートカラーの混沌に映し出されているように、変貌してしまった様相の状態のうちに、1968年にはレッド・ツェッペリンの“Communication Breakdown”やジャックスの“マリアンヌ”が感性に訴えかける非常ベルのように鳴り響いたのだし、前後して白土三平の『カムイ外伝』や山上たつひこの『光る風』も始まっている。どうやら、品行方正で安定しているノスタルジーなどというものから意図的に身を引き剥がし、私たちは、起こりえなかった事後の風景に焦点が合わされ視えてきた、正義と不正義の齟齬や紊乱のありようから始めるしかないようではないか。実際に、ここに長々と引用した日向あき子のテキストのうちに少なからず登場し彼女の美学理論の枠組みの下支えとなったこれらアートの諸形式に――日向や他の多くの人々と相反して――1970年代はおろか2010年代の終わりまでも、ECDは彼の生を通じて殉じたのである。
*1 『他人の始まり 因果の終わり』河出書房新社、2017、p.155。
*2 『ひきがね』島崎ろでぃー写真、ころから、2016。
*3 『いるべき場所』メディア総合研究所、2007、p.149。
*4 『何もしないで生きていらんねぇ』本の雑誌社、2011、p.87。
*5 『暮らしの手帖』、p.198、扶桑社、2009年。
*6 ECDが少なからず影響を受けたミュージシャン、ジョン・ライドンの音楽グループの名前である。
*7 Public Enemy “Caught, Can We Get a Witness?” 1988.
*8 日向あき子「ロックの中の原始回帰」『原始の心』社会思想社、1972、p.103-120。
*9 同前。
*10 『展望』158号、筑摩書房、1972。

Hiroshi EGAITSU
執筆/DJ/PortB『ワーグナー・プロジェクト』音楽監督。立教大学兼任勤講師。90年代初頭より東京の黎明期のクラブでレジデントDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域において国内外で活動。
