newworld
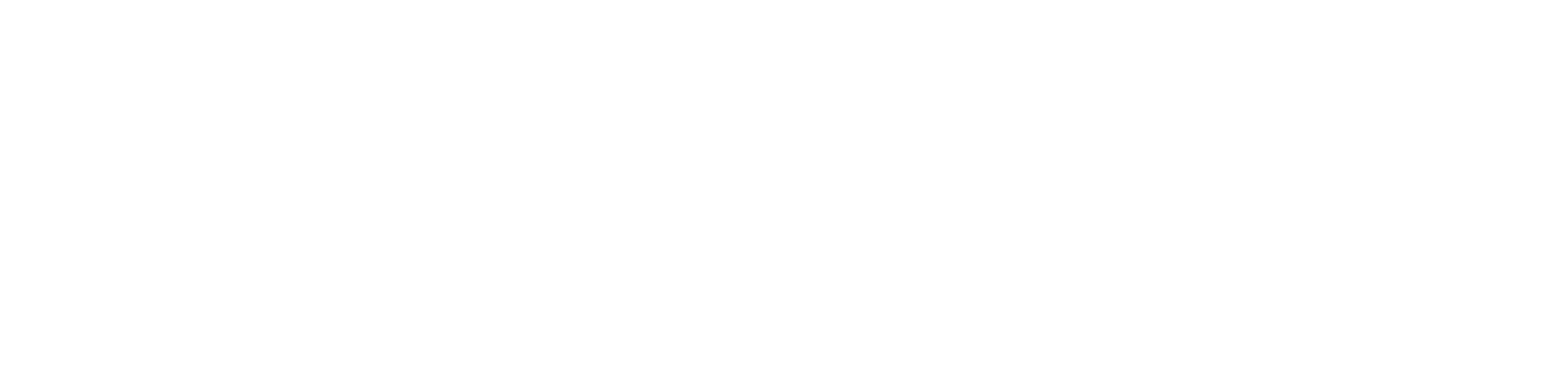
Happy NeWORLD

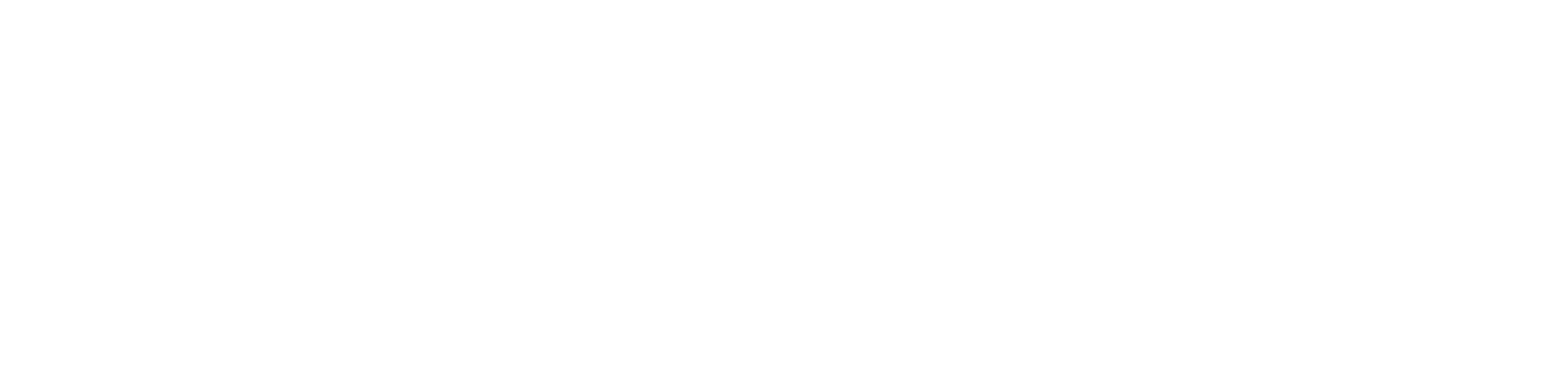
Happy NeWORLD

ECDの愛の詩歌へ再び向かう。
夏になれば公園で盆踊り大会 引っ込み思案でオトナからは会うたびに
「おとなしいね」っていわれてたってのに 吸い込まれてく踊りの輪の中へ
気がつきゃいつの間にやぐらの上 音楽 自分変えた瞬間だ
そっから始まったありゃなんだったんだ それからの人生まさにアップエンダウン
そして失ったものたちと引き換えに こいつがある音楽 それだけでOK
しかもそれ自分で作るみんなが聴く 幸せだなあ君といる時が一番
幸せなんだ たとえ話しで言ってんじゃないからな だから照れてないよ 全然
たどり着いたまぎれもない実感 ウソだろって思う?ほんとの話しなんだ
出来すぎた話だけど誇張は一切なし 君といつまでもって
英語で言うと そう つまり
Together Forever
ふたりを夕やみが つつむこの窓辺に あしたもすばらしい しあわせがくるだろう
ECD×DJ Mitsu The Beats “君といつまでも(together forever mix)”2017
1983年にそれまでヒップホップの地図にまだはっきりと載っていなかったクィーンズはホリスから現れたRun-DMCという3人組が、メンバーの1人の兄であるラッセル・シモンズと共に黎明期のニューヨークのヒップホップの地勢図どころか少なくともポップ音楽の歴史を変えたが、彼らはECDにも大きな影響を与えている。
そうこうしているうちにいとうせいこう&タイニィ・パンクス(高木完・藤原ヒロシ)それに近田春夫といった人たちがこれからはヒップホップだと言ってジャージ姿で登場して『宝島』をはじめとする雑誌の誌面をにぎわせ始めた。僕は八五年には来日したアフリカ・バンバータを観に行っていたし、トミー・ボーイの12インチは相変わらず買い続けてもいた。しかし、パンクに飛びつくことでグラム・ロックで知り合った仲間から孤立してしまったように、この時まだ僕にはヒップホップを聞く知り合いがいなかった。いとうせいこう、高木完、藤原ヒロシという人たちのことはよく知らなかったが、僕にとって、そこに近田さんが混じっていたことの意味は大きかった。もう、ひとりじゃない、そう思えたのだ。もっとも彼らが一押しするラン・DMCについて僕はまだ聴いたこともなかった。それが初めてラン・DMCの「マイ・アディダス」を聞いて一週間もしないうちに僕は原宿のDEP’Tで買ったスーパースターをヒモ無しで履き、ラン・DMCのロゴが入ったカンゴール・ハットを被っていた。デフ・ジャムのレコードを探して東京中の輸入レコードを回った。もう、頭の中にはヒップホップしかなかった。[1]
1984年のホリス公園でのライヴと曲名に説明のつく“Together Forever”は、1985年にリリースされたRun-DMCの9枚目のシングルである。1990年代にECDはヒップホップから“降りた”だろうが、2017年に彼が書き遺した、その生涯に渡る思いを伝えるこの切ないラヴレター自体がラップであるだけでなく、初期のヒップホップはが決定的な存在感を誇るのであり、おそらく、この曲の名前である“君といつまでも“を“Together Forever”と英訳するところからこのラヴレターの下書きは始まったのであろうという推測さえ可能なのだ。
ほぼすべてのラップは、どこか離れた「よそ」についての空想物語についてラップをしているのではなく、「ここ」についてより始まるのだ。例えば、マイクを握るラッパー自身がいかに優れているかをラップする。1970年代ニューヨークの黎明期のラップであったら、必ず彼(彼女)のバックのDJの持つ驚くべき技術についてラップがあっただろう。もしくは彼(彼女)の肢体がいかに性的な魅力に満ち溢れているか、また彼(彼女)がいかにストリートでの勢力を握っているかをラップする。次にはその過程から、今度は彼(彼女)を取り囲む観客や、自分たち全体が属しているコミュニティについてのラップが生み出されていくだろう。ラップ/ヒップホップは、その始まりから自分(たち)がいかに優れているかということ自体についてラップしていたし、それ以上に重要なのは、それについてしかラップは可能ではなかったのだ。このことについてはこの連載の後に詳しく触れることになる。
“頭の中にはヒップホップしかなかった”と回想される1987年から実に31年が経過しての2017年にECD/石田義則が依然としてそのこと――“こいつがある音楽 それだけでOK”とラップするのに耳を傾ければ、ここで言及された音楽即ちラップであるゆえに、ヒップホップ誕生時からのラップの持つ構造の特徴を受け継いでいるように思える。マイクを握るラッパーが優れた彼自身について言及するというのは、誰も知り得ない「どこか」にいる「真正」の「彼」についてなどではなく、「今」「ここ」に取り囲む観客と共にいる「彼」についてであるのだから、すべてはとりもなおさず(彼の)「ラップ」が優れていることから始まる。
彼が終わりのないセックスをいつでも手に入れられるのも、彼の非合法な行為のお目溢しのほのめかしも、もしくは実は――つまり「よそ」では――子供たちにとっては彼が優しい父親であるということも、それは目の前でパフォームされるラップから拡がりだしていくものだ。その関係の端緒のありようにおいて“君といつまでも(together forever mix)”は、1970年代のサウス・ブロンクス以来のラップ/ヒップホップの基本的なフォーム/コンテントとそのパフォーマンスの関係の構造のうえに成り立っている。
しかし、この曲はラッパーが自身(のラップ)を誇ることによって始まる、エゴイズムの意匠が駆動する欲望の装置で終わらない。ECDが子供時代を過ごし体験した高度成長期の日本におけるナショナルなアイコンの、最もよく知られているヒット曲のフックを使いながらその意味を転倒させヒップホップ/ラップに仕立て上げることは、自意識の織りなす寓話の範疇に収まるものよりもしろ、アートについてのアート、ポップ音楽についてのポップ音楽(ラップ)による言及という再帰的な、ポップ音楽論ともいうべきものに近付いていく。
小さい頃のことを余り憶えていない。しかし、音に関する記憶をたどると、その音と同時に当時の光景もよみがえる。初めて自分で歌った歌が何だったか憶えていない。そのかわり、自分が初めて作った歌(?)ならはっきり憶えている。僕には二つ下に孝二という弟がいる。まだ小学校にあがる前だったと思う。
「コージ、コージ、イシダコージ、頭の中が工事中」
僕はそう節をつけて歌って弟をからかった。その頃、家の中はフェンシングの防具で一杯になっていた。ミシンで布の部分を縫い合わせるのが母の内職だった。
六三年の一月には『鉄腕アトム』の放映が始まっている。しかし、僕は当時『鉄腕アトム』を観た記憶がない。ところが同じ六三年の十月に始まった『鉄人28号』十一月に始まった『エイトマン』『狼少年ケン』については、主題歌が流れるタイトル・バックをひとつひとつ細部までまざまざと思い出すことができる。さらに六四年の『少年忍者風のフジ丸』『ビッグX』六五年の『スーパージェッター』『宇宙少年ソラン』『W3』『オバケのQ太郎』『ジャングル大帝』『ハッスル・パンチ』どれも、主題歌を今でも口ずさむことができる。反面、幼稚園で習ったはずの歌はよく憶えていない。
六六年、僕は小学校に通い始める。流行歌、歌謡曲が子供たちの間でも歌われるようになる。学校の行き帰り、道路工事の現場があると、僕たちは必ず
「父ちゃんのためならエンヤコーラ、母ちゃんのためならエンヤコーラ、もひとつおまけにエンヤコーラ」
と、丸山明宏の「ヨイトマケの唄」(六六年)の冒頭部分を声を合わせて歌いながら通り過ぎた。二年生になった六七年にはブルーコメッツの「ブルーシャトウ」の替え歌が子供たちの間で大流行した。
「森トンカツ 泉ニンニク かーコンニャク まれテンプラ」
子供が二、三人集まると何かのキッカケで誰かが歌い出し、皆で笑うのだった。同じように、六八年にヒットしたフォーク・クルセーダーズの「帰ってきたヨッパライ」も子供たちに人気を博した。この曲は僕自身にそれまで聞いたどの歌とも違う強い印象を残した。テープの早回しで加工された、それまで聞いたことのない歌声は単なる面白おかしさだけではなく、「新しさ」に触れることの喜びを教えてくれた気がするのである。同じようにこの頃、学校の友達とは一緒に唄わなくても、自分だけで好きになる曲がチラホラ出始める。城卓也の「骨まで愛して」(六六年)もそのひとつだ。
「骨までー骨までー骨までー愛して欲しいのーよー」
という強烈なサビが小学一年生の頭にこびりついて離れなかったのである。ザ・スパイダースの「風が泣いている」も好きな曲だった。僕はこの曲を「カッコいい」と思った。音楽に対して「カッコいい」と思った最初の体験だ。
「ゴゴゴー 風が泣いている ゴゴゴー
ゴゴゴー 風が叫んでる」
そんな寂しい歌である。当時の自分にとってカッコいいというのは寂しさに立ち向かう姿のことだったのだろう。[2]
城卓矢“骨まで愛して”1966
例えば、たまたま彼の書き遺していった著作に見出されたある頁によって、こうしてECD/石田義則の生きざまの一面はその始まりから言葉のリズムやライミングと結びつけられる。他のすべてのラップと同じようにどこか「よそ」ではない「ここ」にまつわるこの”“君といつまでも(together forever mix)”のラップは、翻って人はいかに生きるのかという古典的といえる問いへも私たちを導いていく。人は1回しか生きることができないのだから、幼い子供の時分に音韻に魅かれた人間が少なくとも50年という買い戻し不可能な時間をラップに捧げたという否定のしようのない事実が、分厚く長いドイツの小説に書かれていたように、この数分間をあの芸術と人生の関係にまつわるものに化していく。

パフォーマンスや詩でも小説でも、もしくは映像作品でも、当初はどのアーティスト誰しもが平凡な暮らしの必要に迫られてその場凌ぎの不定形なものを生産することから始まったとして、その創造を持続させていくことによって、何か一つの通底した構造を与えることにより何かが見開いていくような契機へそれを導くことは可能だろうか。もし可能だとするなら、それは例えば僧のように、いつ終わるのかも知れず自らをも芸術作品/悟りへ限りなく近づけていく営為として創造/修行の実践を捉えることによって、ある種の救済へ向かおうとすることになる。
ねえどしたら君といつまでもいられる? どこにある答え?ここ ここにある
リアル つかめない夢じゃないはず ほっぺたつねる それをたしかめる
音楽って名前の君といつまでもって そんなこと言ってたら
「なーに言ってんの、わたしとでしょっ?」ってマジつねられた
そう、もうひとつのリアルに…
“君といつまでも(together forever mix)”はポップ音楽によるポップ音楽論であると同時に、ECDの現実の世界の方を司っている石田義則が結婚していた実在するパートナー植本一子との愛の暮らしにも触れる。音楽のもたらす非現実的な恍惚がいかに自分の生きてきたうえで支配的であったかとの子供の頃からのエピソードを交え進む語りは、1960年代のテレビ・ドラマのように自分がいかに伴侶に愛されているかの“惚気”のエピソードを付け加えることで最後に転倒し、植本との関係は生涯を賭して愛してやまなかったアートとの比較を通して同じように重さを持つことが告げられ、この音楽(についての音楽)はその外にあると思われる“現実(リアル)”と契りを結ぶ。
こうして、石田義則の現実でありながらラッパーECDの暫定的なヒップホップにおいての“リアル”についての定義というユーモラスな“パンチライン”に結ばれながらこの曲は終わる。彼が子供の頃から馴染みのある曲が、ラップを巡っての1人の男(とその実在するパートナーも込み)のポップ音楽アート(ラップ)論として成就するのは、彼自身が念を押すように書き遺したように、テレビから流れる音楽の音韻に魅了された子供が実際にその50年後にリリースする楽曲の居場所として相応しい。この曲をリリースした後しばらくを経て、1960年に地球に落ちてきた男は傷ましくも変貌した見目で地球からどこかへ離れていった。しかし、彼が意図したように“いるべき場所”に“君(たち)といつまでも”いるという意味において、この曲は彼の生になりえる。この音楽が鳴り響く間、いつでも、その鳴り響いている空間で、つまり「ここ」で、彼の生はアートと等しくとり結ばれるのだから。
[1] 『いるべき場所』メディア総合研究所、2007、p.100。
[2] 同前、p.10。

Hiroshi EGAITSU
執筆/DJ/PortB『ワーグナー・プロジェクト』音楽監督。立教大学兼任勤講師。90年代初頭より東京の黎明期のクラブでレジデントDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域において国内外で活動。
