newworld
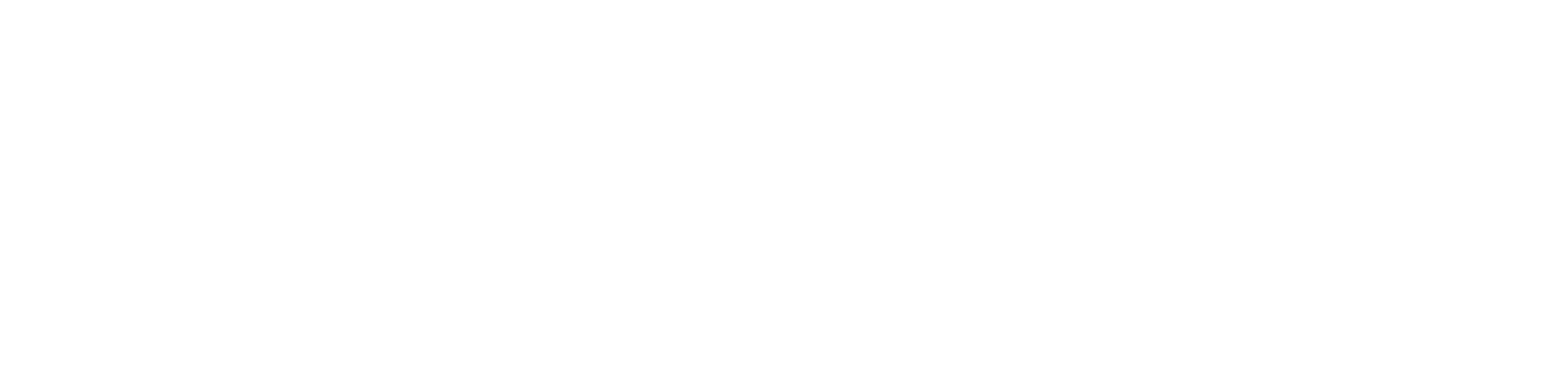
Happy NeWORLD

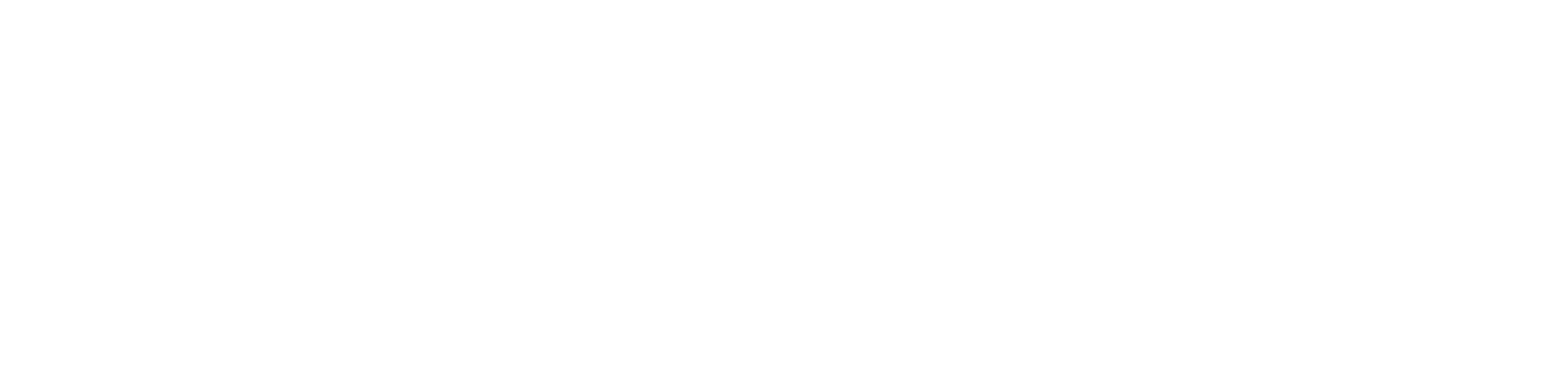
Happy NeWORLD

1969年に発表された小説家・大西巨人のエッセイ集の名前に倣うならば、『戦争と性と革命』の時代、ECDはまだ子供だったが、もしくはそれゆえに、日常生活から脱出する願望の充足として、近所の盆踊り大会を通してダンス・ミュージックを発見した。それを後に原体験として振り返る彼は、他でもない、共同体とアートの関係の重要性について強調したのだ。

テレビを通じてアメリカの家庭に届けられているイメージはそのまま彼の生家であった六畳間の空間に映し出され、母親のそぞろに歌う戦争賛美の映画主題歌を耳にしていた――そんなマスメディアに包み込まれた世代であるECDは、SFテレビ番組『ウルトラ Q』の台詞入りレコードを繰り返し聴くのが好きで、学校の音楽の授業では教師にうまく馴染めず、問題児の友人を通して美術に魅せられたりしながら、結局、ダンス・ミュージックによって自分が変わった瞬間と、持続するビートによってそれが延長され造り出される恍惚の状態に包まれる経験をした。
彼にとってアートが果たす最初の決定的なときは、直接はアカデミズムともマスメディアとも関係なく、気取りなく市井の人々と肩を寄せ合い混じりあうダンスの場、東京の夏の夜の熱気の裡からやってきた。町内というコミュニティの盆踊りをきっかけに、それはそのうちコミュニティ内にもやってきていた手の届くアートから始まりアートを梃子にその外側に何があるのかを彼に発見させ、そこからの離脱を促していくだろう。彼にとって大人の階段を上っていくこととアートが絡み合っていく。そして、この離脱はずっとのちの逆襲とも呼びたくなる彼のそれぞれの場への帰還の行動と連なっていく。
一方、音楽という感覚と感情に訴えかけるアートの形式の洗礼を受けながら、父親が連載漫画“巨人の星”を読むために石田少年に買わせていた週間漫画雑誌『少年マガジン』にさえも侵食していた、“戦争と性と革命”のヴィジョンは、言葉やサウンドだけでなく、言葉とサウンド、そして言葉とサウンドとイメージの関係に、年を経て彼に傾注させていくだろう。
決して裕福とはいえない家庭を舞台に、父権の強制力で誇張するならロボットのように育っていく、当時の流行語ならば“スパルタ”でプロ野球選手として他にない成功を得る子供が主人公の漫画を彼の父親は好む。そのとき石田少年は、“巨人の星”の主人公の家は彼の家より広いことに気がついただろうか。その“巨人の星”ではなく、ECDが思いをもって回想する漫画は、例えば辰巳ヨシヒロの“帆のないヨット”であったが、そこにはヴェトナム戦争を背景に辰巳ヨシヒロの繊細なニュアンスを表現する筆致が可能にした、ほんの僅かなバランスの上に成立する儚い(同性)愛と音楽が描かれているばかりでなく、主人公はアート、つまりは音楽、なかでも“ブラック”の人々の作りあげたカルチャーでもあるジャズのために大学をドロップアウトする。もっとも、それがECDの実際の身の上に起こるのはもう少しあとだとしても。
1972年に石田少年が中学校へ入学したことを機会に、彼の世界は変貌していく。
一体、あと何年あの六畳一間に四人で住み続けるつもりだったのだろう。それが一転して吉祥寺に家を買うことになる。家を買わないかと話を持ちかけてくれたのは、もともと、中野で近所のアパートに住んでいたイシヅカさんである。〔……〕それまで住んでいた家を格安で売ってくれるというのだった。ふってわいたような話に父と母が浮き足立っているのは僕にもわかった。
吉祥寺駅から北へ徒歩二十分、周りは新築の一戸建ての住宅ばかりで単身者が住むためのアパートなどは少ない。そんな中にある六畳と四畳半の二間に台所と風呂場という間取りの築二十年は過ぎた平屋。 [1]
ところで、数多いECDの生前に発表された音楽や文章のうちに、聞いたり読んだりしているこちらの胸が締めつけられるようなものは決して少なくない。それは進みゆく彼の文体が、彼の“リアル”をなるべく透明かつ冷静な描写で思い出し記そうとしているにもかかわらず、ときに何かが彼のその意志を超えてしまっているように感じられる際がいくつもあるからだ。例えば、彼が繰り返し取り上げている中野の生家についての、そこに還ること自体を題材にした“中野区中野1-64-2”という短い文章のこの一節。
三十四年も経っているのだ。てっきりかわりに何か新しい建物が建っていると思っていた。そこにあったのは何もない草叢であった。僕の一家が住んでいた元倉庫のあったその地面だけが取り残されたように丸裸になっていた。六畳一間とはいえ家が建っていたとは思えない狭さだった。三十四年という時間の痕跡が全くうかがえないのだった。 [2]
僕が生まれたのは病院ではない。その家でお産婆さんにとりあげられたのだった。自分が生まれたのは目の前の草叢なのだ。そう思うと自分はかつて人間ではなく猫か何かだったのではないかと思えてくるのだった。 [3]
しかし、この他人にはどうしようもない彼の哀しみをもって描かれる生家と雑多に錯綜する町並みの中野から引っ越した新しい土地――しかも現在ならJRで11分しか離れていない――吉祥寺という空間に彼は馴染めない。
父と弟がどう感じていたかはわからないが少なくとも僕と母は引っ越した当初から、この吉祥寺の町にはっきりとした目に見えない壁の存在を感じていた。 [4]
ほとんどが二階建ての周りの家々からははっきりと見劣りがした。向かいの家の一家の父親はどこかの会社の部長クラスらしく、いつも高級そうなスーツに身を固めていた。母親は家にいる時でもいつも和服だ。ベランダからこちらを見下ろす顔は気取りすましていて、僕ははっきりとこの一家に敵意を抱いた。その母親が弾くのか、それとも僕と同い歳の息子が弾くのか、ピアノの音も時折聞こえてくる。息子とはついの一度も一緒に遊ぶことはなかった。 [5]
「この辺の道路は本当に綺麗に碁盤の目にみたいになってるんだねぇ」
母がそうしきりに感心する。確かにこの辺はきちんと区画整理されている。道路は正確に東西南北に走り、その道幅もほぼ均一だ。だから二十分離れた吉祥寺駅までたった三つの角を曲がるだけでたどり着くことができた。入り組んだ細かい路地の隙間を高さも大きさも違う家々が無秩序に軒を連ねる中野の町とはその外観からして大きく違っていた。特にこのあたりは川もないから土地の高低もなく、真っ平な土地が広がっている。だから真っ直ぐに延びた道路はどこまでも見通せる。缶ケリ遊びをしても隠れるところは電信柱の陰ぐらいしかない。だだっ広くて空気まで薄いような気もする。外での遊び方も中野時代とはすっかり様変わりした。「ローラーゲーム」というテレビ番組に影響された僕は四、五人のグループを組み、ローラースケートを履いて走り易い舗装されたばかりのアスファルトを選んで町中をひたすら走りまわった。その範囲は中学校の学区ほどの広さにまで及んだ。真鍮性のホイールは「ゴーゴー」と容赦ない騒音をとどろかす。ホイールと路面の凸凹が起こす振動が足の裏をジンジンと刺激する。それは頭まで痺れるような感覚を引き起こした。 [6]
吉祥寺に移ってからの母は毎日「ハリアイがない」「家にいるのがツマラナイ」とこぼした。 [7]
新しい土地に着いて暮らしを営む家族がふたつに分けられて、このように価値を判断する尺度になるのは彼と母親の側で、そのことを私たちは忘れないほうがいいだろう。中野と吉祥寺という彼が彼の家族と共に過ごした空間へ私たちもまた後に還り詳しく訪ねていくだろう。しかしここでは、外においての違和と同時に、内において進行していたもう一方の彼の世界の変貌について追う。
石田家では“試験勉強という名目でそれまでは許されなかった子供の夜更かしが公認される”。“夜更かしを覚えると自然とラジオを聞くようになった”。“ラジオはTVやマンガ雑誌では触れることのなかった二つの重要な要素を備えていた”。[8] 彼によるなら、それは性と音楽だ。
後者については、それは日本のフォーク/ロックと洋楽だとECDは記す。同年、彼は聞いたフォークの曲として、吉田拓郎、あがた森魚、岡林信康、高田渡、古井戸、猫、RCサクセション、そして加川良、泉谷しげるまでを挙げる[9]。なかでも最後の2人の、それぞれ“教訓I”と“黒いカバン”は、のちに彼に与えたその影響を回想し著書にその歌詞までを引用する。
命をすてて 男になれと
言われた時には ふるえましょうヨネ
そうよ 私しゃ 女で結構
女のくさったので かまいませんよ加川良「教訓I」より
中学一年といえば第二次性徴期の真っ最中である。その少し前の僕はGSが世の中に広めた髪の長い男か女かわからないナヨナヨした男性像に全く抵抗を感じることはなかった。ところがこの頃になると、僕は過剰といってよいほど「男らしさ」を意識するようになっていた。梶原一騎原作の『愛と誠』のマッチョイズムに魅かれ、恥ずかしいことに、TVの青春ドラマ『俺は男だ!!』の森田健作にあこがれたりした。ところが「教訓I」の歌詞は理不尽なほどの筋が通っている。 [10]
それは「男らしい男になる、ということはよき兵隊になることだと言っているのだ」 [11]と石田少年であった時期を振り返りながら、ECDは記している。
つまり、戦争を否定しようとしたら、自分がよりどころにしようとしていた「男らしさ」というものを否定しなければならないのである。そんな歌を聞いて、自分を守るために「教訓I」の方に嫌悪を感じるという反応をしても不思議はない。しかし、僕はそうならなかった。僕の中では「戦争はイヤだ。お国のためになんか死にたくない」という気持ちの方が勝ったのだった。僕は「教訓I」をもう一度聞きたくて(註:ラジオ番組に宛てて)、初めてリクエスト葉書というものを出した。 [12]

それぞれへの認識が正しくあれ間違っているのであれ、ECDがここでアート(音楽)についての解釈において、既に政治と性(ジェンダー)を結びつけ捉えていることを私たちは忘れないでおきたいが、子供時代に聞いた音楽から歌詞が引用されているもう1曲はいわゆる“職質”にまつわる、イデオロギー批判などに赴かないその表層の事情にとどめられるお話のあざとい巧みさが印象に残る、泉谷しげるの“黒いカバン”である。
黒いカバンをぶらさげて歩いていると
オマワリさんに呼び止められた
「オーイ、チョット」と彼はいうのだった
「オーイ、チョット」というアイサツを
くれたことがなかったので
ムカっときたのです泉谷しげる「黒いカバン」より
「黒いカバン」はこんな調子で始まる。ラップとは違うけれど歌というより喋りに近い。「黒いカバン」の主人公はこの後、「ひとに名前を聞く時には自分から名乗るのが礼儀だろう」と「オマワリさん」への反撃を開始する。その反撃のたくみさに僕は胸のすく思いがした。泉谷しげるは警察への反感を「くたばれ」というような直接的な言葉で表現するのではなく、職務質問の実際の様子をネチネチと描写することで表現した。僕はそこに「知恵」を感じ取り、強く魅かれたのだ。「黒いカバン」は『春夏秋冬』に収録された曲でシングル・カットはされてない。それでもラジオで耳にする機会は少なくなかった。 [13]
騒音で痺れるような感覚でしか知覚しえない、のっぺらぼうでお高くとまりどこまでも平坦な町並み、その点景としての高級そうなスーツや聞こえてくるピアノの響き、こうした、いつのまにか風景を変貌させていたブルジョワ的意識の外部からやって来た者のように、しかし『光る風』やその他の漫画に描かれた暴力とは一線を画し、例えば“黒いカバン”を持つ闖入者のように言葉を巧みに配置することにより、どこからかこの風景を維持し管理している隠蔽された権力と呼ばれる均衡を引き摺り出していく――1970年代、実は既に整えられつつあった海の向こうの新しい文化環境が用意していたヒップホップという手段と遭遇することによって、そのうち石田少年にもそれが可能になる。彼はECDと名乗るようになる。
[1] ECD『暮らしの手帖』扶桑社、2009年、p.12。
[2] ECD『失点・イン・ザ・パーク』、太田出版、2005年、p149。
[3] 同前、p150。
[4] ECD『暮らしの手帖』、p.13。
[5] 同前、p.12。
[6] 同前、p.14。
[7] 同前、p.15。
[8] ECD『いるべき場所』メディア総合研究所、2007年、p.22。
[9] 人物名の記載は登場順。
[10] ECD『いるべき場所』、p.25。
[11] 同前。
[12] 同前。
[13] 同前、p.26。

Hiroshi EGAITSU
執筆/DJ/PortB『ワーグナー・プロジェクト』音楽監督。立教大学兼任勤講師。90年代初頭より東京の黎明期のクラブでレジデントDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域において国内外で活動。
